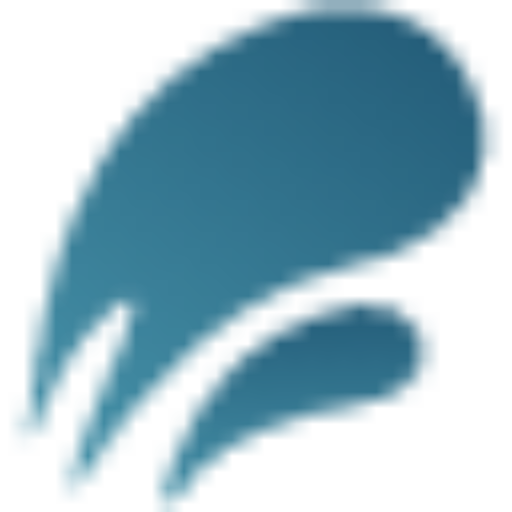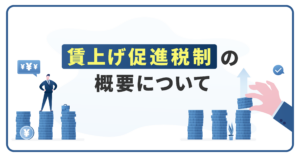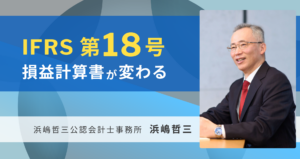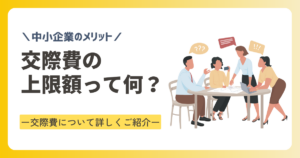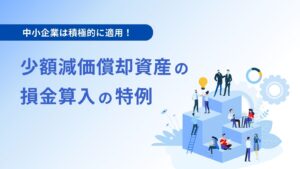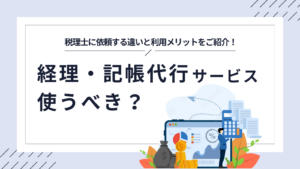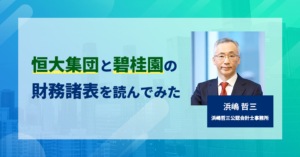令和5年10月より始まるインボイス制度。本稿では、そもそもインボイスが指す内容、制度の概要、そしてインボイス制度が導入される10月までに何をすれば良いのか、インボイス制度導入前の留意事項についてご紹介します。
インボイス制度とは
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といい、軽減税率制度の導入によるタイミングで採用することが決まりました。これまでは、取引の相手方が発行する請求書について、相手方が課税事業者/免税事業者のいずれかに関わらず仕入税額控除の適用を受けることができました。
しかし、今回のインボイス制度の導入によって、仕入税額控除の適用条件に「消費税課税事業者であること」という要件が加わりました。つまり、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除の対象外となったのです。
消費税課税事業者であるという証明として「適格請求書発行事業者」の登録が必須となり、請求書に「適格請求書発行事業者」の登録番号を明記することとなりました。このことから現在は消費税の納税義務がない小規模事業者や個人事業主の売り上げに影響が生じたり、課税業者となることによる税負担や導入のための負荷がかかることが懸念されています。
売り手側の対応について

インボイス制度の開始に伴い、どのような対応および影響が生まれるのでしょうか。 まずは売り手側の対応について説明します。
売り手が既に課税業者である場合には適格請求書の発行が義務付けられますので適格請求書発行事業者としての登録をすべきです。登録を行わない場合には取引先で仕入税額控除が取れなくなることから取引先との間に問題が生じる可能性があります。登録後は請求書に適格請求書発行事業者の登録番号を請求書に記載するようにすることで、基本的な対応は完結します。
売り手が現在免税事業者(設立1期目~2期目の事業者や課税売上高が1,000万円以下の事業者※)の場合には、課税事業者になるか、従来通り免税事業者のままでいるか、慎重な判断が必要です。
というのも、適格請求書発行事業者に登録することで、消費税の納税義務が発生するからです。納税義務の発生に伴い、消費税分の売上を留保できないことになるため、利益が減少する可能性があります。また、 取引先・顧客によっては適格請求書発行事業者の登録を求めてくることも考えられますので、取引先・顧客の意思を制度が開始する前に確認しておくことも大切です。取引先との関係と消費税納義務が生じることによる手取り額の減少とどちらが業績への影響が大きいかを考慮して判断する必要があります。
※事業年度開始日の資本金または出資金が1,000万円以上の法人、特定新規設立法人に該当する法人は除く
買い手側の対応について
続いて買い手側の対応について説明します。
適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者と取引をした場合には、仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。そのため、まずはインボイス制度開始前のタイミングで、既存の取引先が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかを確認する必要があります。後述する通り適格請求書発行事業者の登録が行われているかどうかは国税庁の公表サイトで確認することができますので取引先に登録番号などを問い合わせるのが良いでしょう。
そして、適格請求書発行事業者に登録されていない取引先が存在した場合には、登録を行っていない理由、そして今後も登録を行わない予定なのか等、取引先の状況を確認するのが良いでしょう。後述する通り経過措置は存在するものの、仕入税額控除の適用を受けられない場合には、利益の減少につながる可能性もあります。適格請求書発行事業者の登録をしていない取引先には、仕入税額控除が取れなくなることを伝えたうえで、制度開始後の対応を話し合い、お互いに誤解が生じないようにしたうえで制度開始を迎えるのが良いでしょう。
また、令和5年10月に制度が開始された際には、取引先から送付される請求書に「適格請求書発行事業者」としての登録番号が明記されているか、必ずチェックするようにしましょう。さらに、インボイス制度においては電子帳簿保存法に基づく対応が必要となります。電子帳簿保存法の対応方法については別記事で解説していますので是非ご覧ください。
インボイス制度の登録について
インボイス制度の導入時には、課税業者である法人や個人事業主は「適格請求書発行事業者」として登録している必要があります。適格請求書発行事業者に登録した場合にはTから始まる番号を税務署より付与されるので、この登録番号が付与されていれば、適格請求書発行事業者としての登録が完了です。
登録を受けるためにすべき事
「e-Tax」または「郵送」にて以下の「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄税務署へ提出する必要があります。 申請書の様式は以下にてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf
その他の留意すべき事項
インボイス制度が導入される前に今何をすべきか、以下留意事項目を踏まえながら解説していきたいと思います。
適格請求書発行事業者を確認する方法
インボイス制度開始に当たって、仕入先・取引先から届く適格請求書に記載されている登録番号が正しいものであるかどうか確認する運用が必要となります。取引先が適格請求書発行事業者に登録されているかどうかは国税庁の公表サイトで確認することができます。
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
経過措置について
インボイス制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。以下の通り仕入税額控除が受けられる金額は段階的に小さくなりますが、インボイス制度導入の影響は一定程度緩和されることになりますので自社または取引先が免税事業者の場合には、経過措置の内容も踏まえて対応方針を検討したほうが良いでしょう。
第一段階:令和5年10月1日から令和8年9月30日までの免税事業者からの仕入れについては、80%が仕入税額控除の適用を受けることができます。
第二段階:令和8年10月1日から令和11年9月30日までの免税事業者からの仕入れについては、50%が仕入税額控除の適用を受けることができます。
簡易課税方式の影響について
「簡易課税方式」を採用している事業者については、仕入税額控除を受けるために適格請求書は必要なく従来通り以下の計算式で消費税額の計算を行います。
(計算式) 消費税納入金額 = 課税売上に係る消費税額 × (100% ー みなし仕入れ率)
そのため、簡易課税事業者の場合は仕入先が適格請求書発行事業者であることは関係なく、従来通りに仕入税額控除を受けることが出来ます。
一方、販売先が「一般課税方式」を採用している場合、適格請求書の発行を求められる可能性があります。
簡易課税事業者になるためには基準期間である前々年事業年度の課税売上高が5,000万円以下であることが条件となります。また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。免税業者が適格請求書発行事業者に登録する際に簡易課税制度の適用を受けたい場合には、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出時にあわせて「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで簡易課税制度の適用を受けることができます。
申請書の提出が遅れた場合の影響
申請書の税務署への提出が遅れた場合の法的なペナルティ・罰則などは一切ありません。
しかし、申請書を提出してから適格請求発行事業者に登録され、登録番号が通知されるにはおおよそ1か月ほどの期間を要します。そのため制度開始のギリギリに提出を行うと、インボイス制度が始まる2023年10月に登録番号が明記された適格請求書を発行できないリスクが発生します。適格請求書が発行できなかった場合の最悪のケースは、取引先から取引を解約される可能性があるため、申請書の提出は忘れずなるべく早めに済ませておくべきです。
また、適格請求書を発行する際には業務プロセスや自社システムの設定変更などの作業が伴うことが多いです。申請作業を実際に行わないとイメージが湧かないことも多いため、この観点からもなるべく早めに申請を済ませておくべきと言えるでしょう。
おわりに
本稿では、インボイス制度の概要と登録スケジュールや登録方法などについて解説しました。また、インボイス制度が開始された際に、適格請求書発行事業者への登録が行われていない場合には、取引先との関係に影響が生じる可能性があるなどの留意事項もご紹介しました。適格請求書発行事業者の申請書の提出期限が近づいてきているため、インボイス制度にどう対応すべきか悩んでいる方は最寄りの税務署や税理士へご相談されることをおすすめいたします。