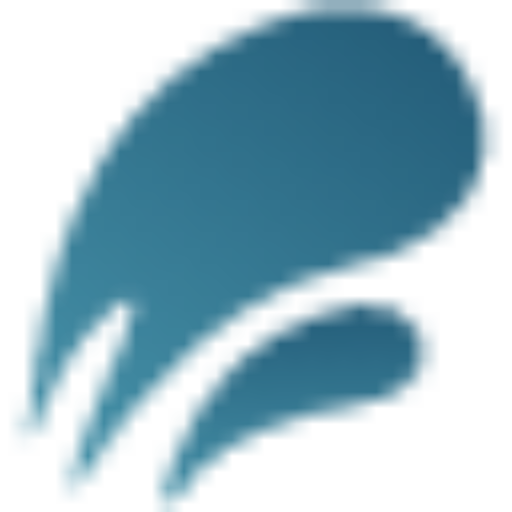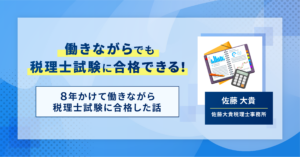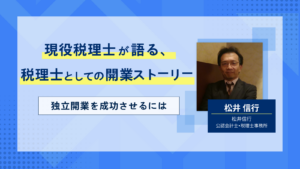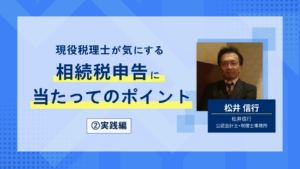昨今、相続対策や親の認知症対策として家族信託が話題になります。
そこで本記事では税理士が家族信託をクライアントに勧めるべき3つの理由 と題し、家族信託の概要、勧めるべき理由、留意点、課税関係についてご紹介します。
家族信託とは
家族信託とは信託法に依拠して組成される資産管理の手法といえます。家族信託の主な登場人物は3人で、資産をお持ちの方(委託者)が当該資産を信託財産として拠出して、親族の方(受託者)に当該資産の管理や処分を任せ、信託財産から得られる利益を受け取る人(受益者)を定めて家族信託契約を結び実行します。
この時、委託者と受益者を別の方にしてしまうとその時点で委託者から受益者への贈与となるのが原則ですので、家族信託を組成する場合は、委託者=受益者とすることが一般的なケースです。
また信託財産の名義は受託者となります。受託者固有の財産と信託財産とは分けて管理する必要があるため、不動産は登記をする必要があるほか預貯金等の信託財産は信託口座を作成して管理する必要があります。
家族信託の期間をいつまでに設定するかについては画一的な基準はなく、家族信託の目的に沿って検討することとなります。
一般的なケースとして例えば、委託者の認知症リスクに対応することを目的として利用する場合は委託者の死亡を契機に家族信託を終了させるように設計することが考えられます。
その他、委託者に高齢の配偶者がいる場合には両者の死亡時点までを信託期間とする設計も考えられます。
家族信託における基本的な特徴
成年後見人等に対する報酬が不要
後述の成年後見人制度では、成年後見人に対する報酬(月数万円)及び成年後見監督人に対する報酬(月数万円)が発生しますが家族信託においてはそれらが不要となります。
但し家族信託契約においても、受託者に対して報酬を支払う設計にするケースや家族信託組成のためにはそれなりの専門家報酬(契約内容の検討、作成など)がかかります。
後見制度に比べて柔軟な対応が可能
認知症になった場合の対応という意味では後述の成年後見制度においても対応が可能ですが、家族信託においては信託財産の処分が可能等、より柔軟な対応が可能です。
遺言書としての機能
信託終了時(委託者=受益者死亡時)の信託財産の帰属者を定めることで、当該帰属者に資産を取得させることができ、遺言書としての機能を持たせることができます。
成年後見制度
成年後見制度は民法に定められている制度です。認知症などで意思能力がなくなってしまった場合には、預金の入出金や法律行為に制限がかかってしまいますが、成年後見人を付けることで、意思能力のない方(成年被後見人)に代わってそういった行為を行うことができます。
成年後見は家庭裁判所に選任してもらい、弁護士や司法書士等の専門家が選任されるケースが4分の3程度、親族の方が選任されるケースが4分の1ほどのイメージです。
成年後見制度の趣旨は、成年被後見人の財産をその方に損害を与えないように管理していくこと(や身上保護)であるため、不動産の処分を進めたり、生前贈与を進めたりすることは出来ないのが原則です。
任意後見制度
任意後見制度は、本人の意思能力があるうちに任意後見人やどういった内容を任意後見人に任せるかを定めて任意後見契約を結ぶことで、認知症等もしもの場合に備えておく制度になります。
本人が認知症等になった場合には家庭裁判所にて任意後見監督人を選任してもらうことで任意後見契約の効力が生じることとなります。
被後見人の財産の積極的な処分に制限があることは法定の成年後見制度と同様ですが、任意後見人を自分で決めることができることがメリットといえます。また、後見制度と家族信託は互いに対立するような制度ではないため併用での活用も検討可能です。
家族信託をクライアントに勧めるべき3つの理由
税理士は、クライアントの資産管理や相続対策における身近な相談者として、サポートしやすい立場にいます。資産の管理という意味では、本人が認知症等になった場合に資産の処分に制限がかかるリスクがありますが、家族信託ではそういったリスクに対応することが可能です。
相続対策で課題となるのは納税資金、遺産分割、節税対策といったところになりますが、家族信託を利用することで主に遺産分割(どのように資産を引き継いでいくか)という課題に対応することができます。
また、家族信託を利用することで柔軟な資産の処分(生前贈与や二次相続を考慮した遺産分割など)ができる結果、節税につながる可能性も十分あります。
1. 認知症リスクへ対応としての活用
家族信託を利用することで、本人が認知症になった場合のリスクに対応することができます。
認知症リスクに対応するために家族信託を利用するケースとしては以下が考えられます。
ゆくゆくは自宅を売却して、介護施設の入居費用としたいケース
認知症になってしまうと自宅の売却にも制限がかかってきます。自宅の売却資金を介護施設の入居費用に充てたいと考えている場合に、自宅を信託財産として家族信託を活用することで、認知症になった場合にも自宅の売却を進めることが可能になります。
本人が高齢になってきており、認知症となるリスクがあるが、多額の資産を所有しており生前贈与を進めたいケース
認知症になってしまうと法律行為に制限がかかってしまうため、生前贈与といった相続対策もできなくなってしまいます。本人の意思能力があるうちに家族信託を活用しておくことで、認知症になった後も信託財産の生前贈与を進めることが可能です。
2. 遺言書としての機能の活用
家族信託には、信託終了時の信託財産の帰属者を定めることで、遺言書としての機能があります。特定の者に財産を取得させたい場合の対応としては、遺言書を作成することでも同様の効果が得られます。
加えて、家族信託の場合には、委託者(当初受益者)が死亡したあとの受益者(第二受益者)を定めたうえで当該受益者が死亡した後の受益者(第三受益者)を定めることもできる点が家族信託ならではの仕組みといえます(受益者連続信託)。
受益者連続信託を活用するケースとしては以下が考えられます。
配偶者との間に子がおらず配偶者が亡くなった後の承継先を指定したいケース
配偶者との間に子がいない場合には、資産は配偶者と直系尊属または兄弟姉妹に相続されますが、本人の死後、配偶者が取得した財産を配偶者の死後は本人の血族に取得させたいケースが考えられます。
こういった場合において、受益者連続信託を利用することで、本人の希望に沿った財産承継を進めることが可能になります。
不動産の共有問題への対応
親族等で共有の不動産を第三者に売却したい場合には、共有者全員が不動産の売却に賛成していることが前提となります。共有者の関係が悪化したり、連絡が取れなくなってしまった場合には、当該不動産が塩漬けになってしまうリスクも十分考えられます。
そこで、共有者の関係が良好なうちに家族信託契約を結んで、財産管理は特定の受託者に任せたうえで、もともとの不動産の共有者を受益者とすることができます。
不動産から得られる利益は共有者で分け合える一方で、財産の管理、処分を受託者に任せる契約にすることで、共有者の理解を得つつも機動的な財産の処分が可能になります。
家族信託を進める際の留意事項

家族信託は専門性の高い分野であり、思わぬミスで当初の目的を達成できない契約となってしまうことも考えられるため、活用するにあたっては慎重な検討が必要です。
家族信託を利用する場合の留意点
受託者を誰にするか
家族信託契約においては受託者が財産を管理していくこととなるため、委託者の希望に沿った管理を進めてくれる信頼できる受託者がいるかは十分に検討しなければなりません。
また、受託者には財産の管理や帳簿の作成など相当の負担がかかるため、そういった大変なことを引き受けてくれる方がいるかという面でも検討する必要があります。
遺留分侵害額請求への対応
委託者の死亡によって取得される受益権等について、遺留分を考慮した家族信託契約を作成することが必要です。
専門家が少ない
家族信託契約を作成、実行していくにあたっては、弁護士、司法書士などの専門家のサポートを受ける必要も出てくると考えます。
ただし家族信託に精通している専門家は少なく、実際の家族信託契約作成にあたっては手探りでの対応となることも十分考えられます。
クライアントにはそういった状況も理解してもらえるように説明する必要があります。
家族信託の課税関係
家族信託の課税の基本
家族信託では、委託者=受益者と設定すること(自益信託)が通常となります。この場合、信託財産の所有権は受託者に移転するものの税法上は経済的利益の帰属に着目して課税される取り扱いとなっているため、(受託者への)贈与税の課税は発生しません。
信託期間中に信託財産から発生する収益、費用については受益者に帰属するものとして所得税が課税されます。この際、信託不動産から生じる不動産所得が損失の場合は不動産所得の計算上なかったものとされるほか、信託契約が複数ある場合には信託契約間の損益通算ができない点に留意しなければなりません。
委託者の死亡により家族信託契約が終了した場合には、当該信託の残余財産を取得する者に対して、当該残余財産を当該信託の受益者等から遺贈により取得したものとみなして相続税が課税されます。
まとめ
家族信託は適切に活用することで多くのメリットを享受することができます。しかし、高度な専門知識を要する分野であるため、活用する際には慎重な検討が必要です。
必ず専門家と相談しながら進めることをお勧めします。