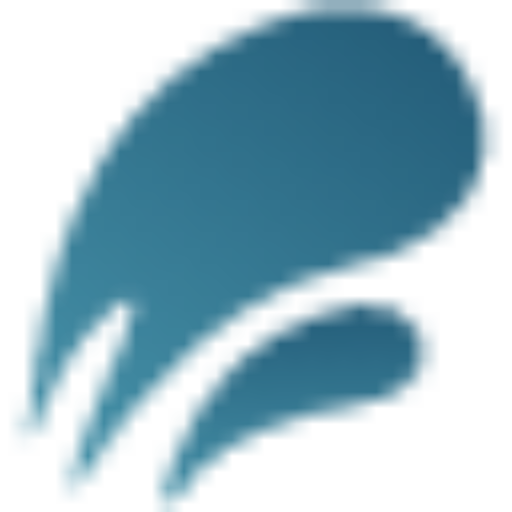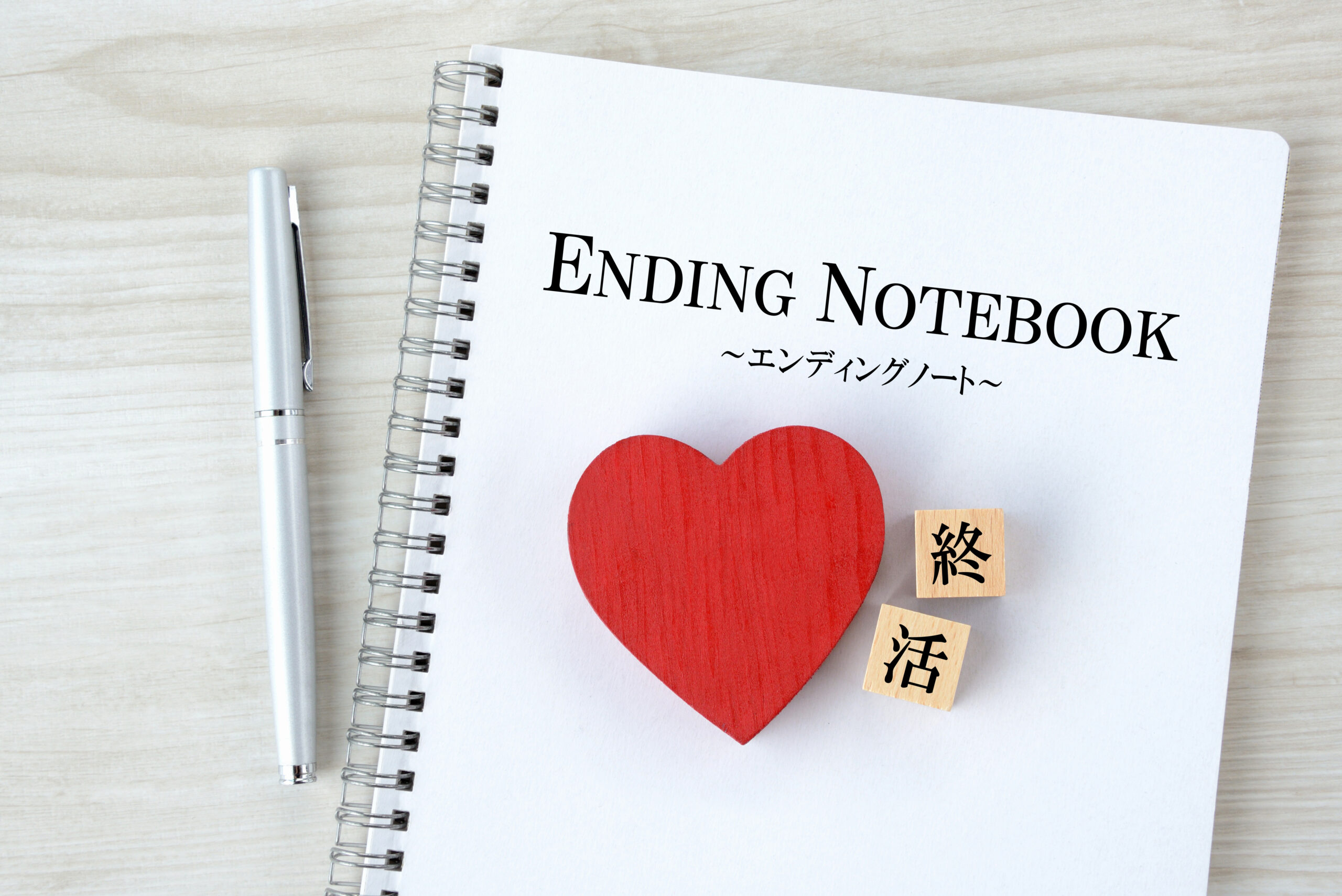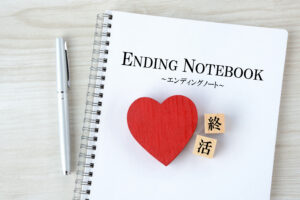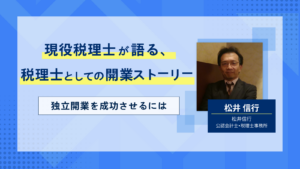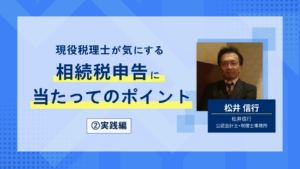かつては富裕層の悩みのイメージが強かった相続税の問題ですが、平成27年の税制改正で基礎控除額が引き下げられて以降、一般的な家庭でも他人事ではなくなってきました。
また相続税がかからない方であっても、不動産や預金、証券口座の相続手続きは皆様必要になってきます。相続発生後にはお葬式の準備や役所への連絡、財産の相続手続きなど、相続人にとって多くの手続きが必要となります。
相続後の心配をされている方や自身の死後のことに不安を抱いている方もいらっしゃると思います。気軽に取り掛かれる相続対策としてエンディングノートの作成がそんな悩みにお応えすることができるかもしれません。
エンディングノートとは
エンディングノートとは、被相続人にもしものことがあった際に家族等に見てほしい情報をまとめたノートです。
一般的には、被相続人が所有している財産の情報や遺言書の有無、家族へのメッセージなどを記載するものとなりますが、遺言書のように決まった形式はなく、自由な内容で作成することができます。
また、遺産分割についての希望を記載したからと言って遺言書のように法的効力はありません。
エンディングノートを作成するメリット
エンディングノートを作成するメリットとして、被相続人にもしものことがあった際の家族の負担を軽くすることができることが挙げられます。
相続発生後には、お葬式の準備から、役所への連絡、銀行や証券口座の相続手続き、保険金の請求、遺産分割協議、相続税申告など多くの手続きが必要になります。そこでエンディングノートに被相続人がどういった財産を所有しているか、緊急時の連絡先、ネット口座のIDとパスワードなどといった情報をまとめておくことで、相続後の手続きを進めていく助けになります。
また、家族への思い、ペットの世話について、被相続人の死を伝えてほしい友人、葬儀への希望など、被相続人の死後に伝えたいことまたは気になっていることをエンディングノートに記載することもできます。
エンディングノートに記載すべき内容
先述の通りエンディングノートを作成しておくことで、相続後の手続きを進める助けになります。具体的にどのような情報を記載しておけば有用なのか、以下でみていきましょう。
遺言書の有無
相続が発生したとき、相続人が複数いる場合には相続財産は相続人の共有となります。
遺言書がない場合には遺産分割協議をすることによって、相続開始の時に当該分割協議の内容で各相続人が財産を取得したことになり、遺言書がある場合には、遺言の内容で各相続人が財産を取得したことになります。
以上のように遺言書がある場合とない場合とでは、相続後の対応が大きく変わるため、遺言書の有無を明確にしておくことは重要です。
また法務局での保管としていない自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認を受けたうえで相続手続きに使用することとなります。
所有している財産や債務のこと
家族であっても被相続人がどこに預金口座や証券口座を持っているかを正確に把握していることは少ないと思います。口座の存在が知られずに相続手続きや相続税申告が進められてしまうことも十分考えられます。
そのため、どのような財産を所有しているかを網羅的に記載しておくことは遺された家族にとって非常に役立つ情報といえます。
また、保有しているクレジットカードや保険契約についても一覧にして、連絡先などを記載しておくことで、相続発生後の手続きを進める助けになります。
金融機関のネット口座等のID、パスワード
相続が起こった場合に、被相続人のネット口座が分かれば、どれくらいの財産を持っているかすぐに確認することができます。また、葬儀費用などの捻出のために被相続人の口座から引き出して支払いをすることはままあることだと思います。
亡くなった後にかかる費用を事前に準備しておくケースはあまりないと思いますので、金融機関のネット口座等のID、パスワードを記載しておくことも、もしもの時には役立つでしょう。
その他、利用しているパソコンやスマートフォンなどの電子機器のパスワードも記しておくことで、電子機器やデータの処分をスムーズに進めることができます。
定期購入しているサービスやSNS
定期購入しているサービスやSNSについても、解約や退会の手続きをすることになりますので記載しておくとよいでしょう。
伝えておきたいこと
上記のほか、エンディングノートを利用して、身近な人に伝えておきたいことを記載しておくこともできます。
法的な拘束力はありませんが遺産分割への希望を記載することもできます。また、葬儀についての希望、ペットの処遇をどうしたいか、被相続人の死を伝えたい人、相続税申告をお願したいと思っている先生など自由に記載することができます。
相続発生後に必要となる手続き(参考)
相続発生後には多くの手続きが必要となることに触れましたが、主な手続きと期限(期限目安含む)は以下の通りです。
| 手続き | 期限 |
| 死亡診断書の取得、提出 | 死亡から7日以内 |
| 死亡届の提出 | 死亡から7日以内 |
| 火葬、埋葬許可申請 | 死亡から7日以内 |
| 葬儀の準備 | |
| 世帯主変更届出 | 死亡から14日以内 |
| 公的年金の受給廃止手続き、未支給年金の請求 | 死亡から14日以内 |
| 国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険の資格喪失届の提出 | 死亡から14日以内 |
| 遺言書の有無確認、法定相続人の確認、相続財産や負債の確認 | |
| 遺言書の検認 | |
| 生命保険の支払い請求 | |
| 公共料金の解約、名義変更手続き | 死亡から1か月以内 |
| クレジットカードや定期購入サービスの解約 | 死亡から1か月以内 |
| 相続放棄や限定承認をする場合の申立て | 死亡から3か月以内 |
| 準確定申告書の提出 | 死亡から4か月以内 |
| 遺産分割協議 | |
| 相続税申告書の提出 | 死亡から10か月以内 |
| 遺留分侵害額の請求 | 死亡から1年以内 |
税理士がエンディングノートを顧客に勧めるべき理由
ここまでエンディングノートやそのメリットについて説明いたしましたが、税理士にとってのよい点は、お勧めしやすい点です。
特に決まった様式もなく、報酬も発生しないため、「それでしたらエンディングノートというものもございますので…」という形でお勧めしやすいです。
被相続人からすると、家族の負担はできるだけ少なく抑えてあげたいですし、ご家族がお亡くなりになり、ただでさえ大変な時期に期限付きでやるべき手続きが膨大にあることを理解いただければ、自然にお勧めすることが可能です。
また、エンディングノートの作成中に遺言書作成の希望が出てきたり、エンディングノートの記載内容の相談に乗っているうちに、生前贈与の話や、不動産の購入や売却の話が出てきたりと、先生方のお仕事につながるような依頼が出てくることも考えられます。
1番有難いケースとしては、お亡くなり後の連絡先として、“相続税申告書の作成はこの先生にお願い”という形でエンディングノートに記載いただけることです。
エンディングノートをお勧めする際の注意点は保管場所です。
もしものことがあった場合には当然見つけてもらわなければならないですが、基本的にとてもプライベートな情報を記載することになるので、生前から目につくような保管場所や第三者に見られるような保管場所は避ける必要があります。