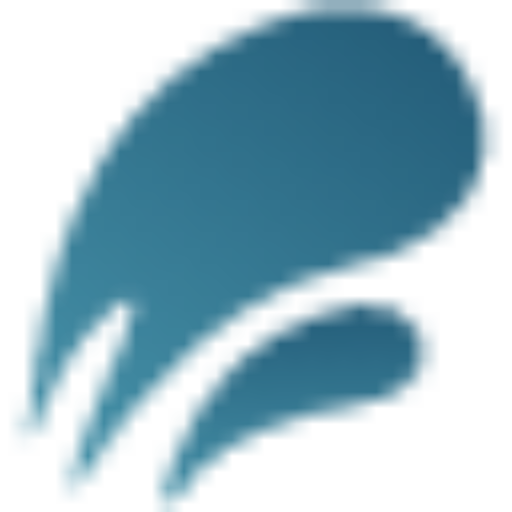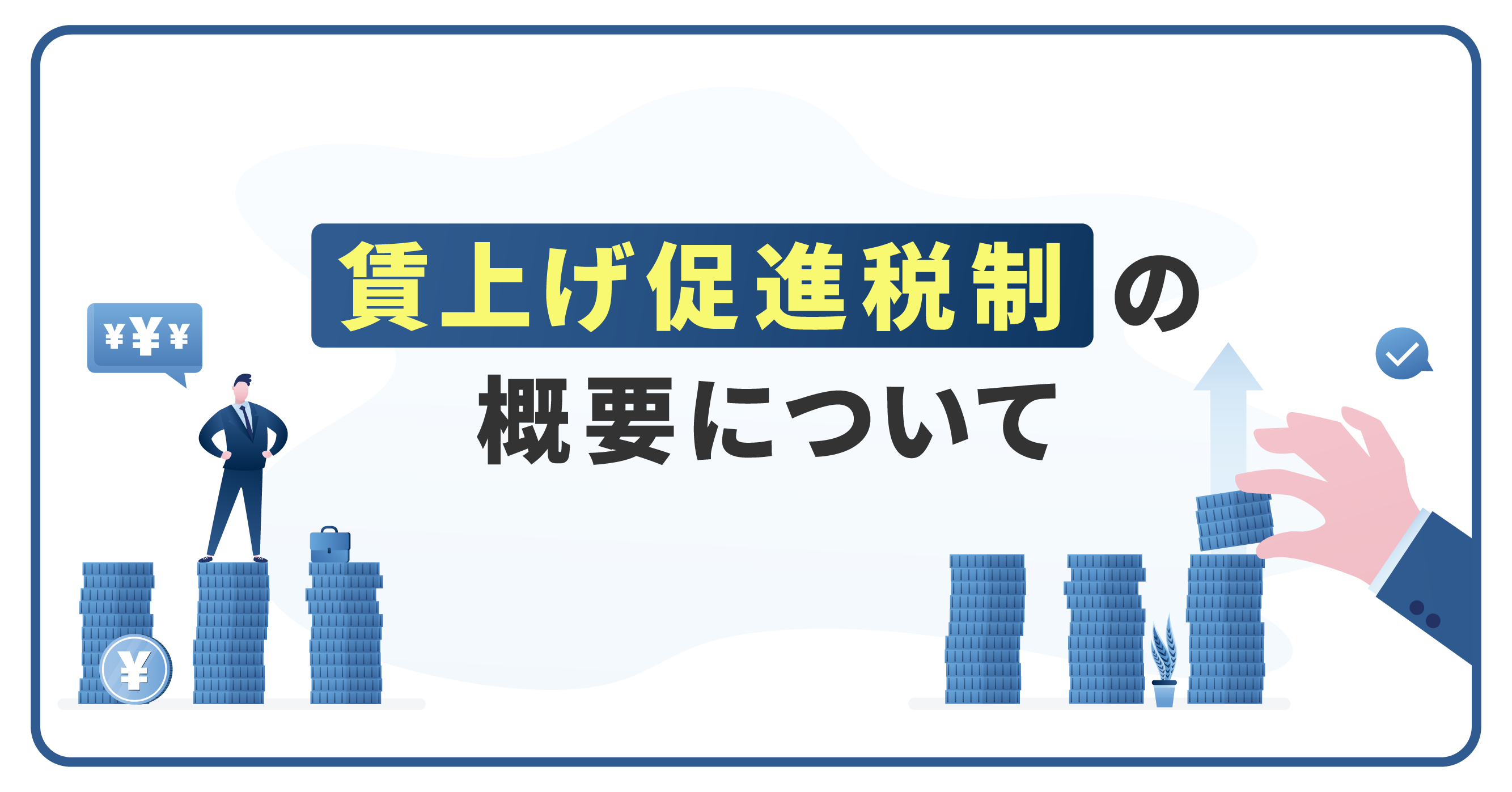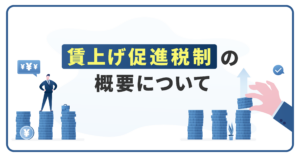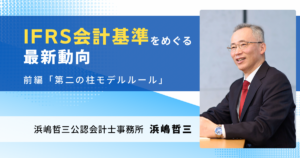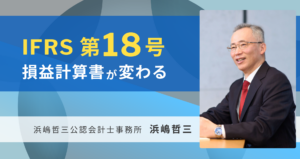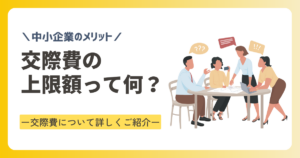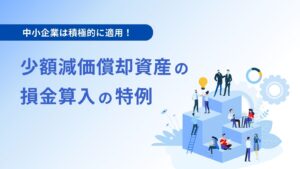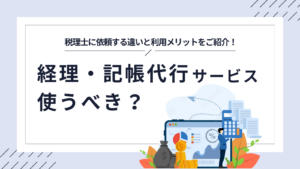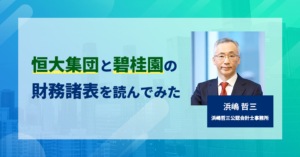令和4年税制改正において最も大きな改正項目の一つとして賃上げ促進税制がありました。令和4年4月1日以降に開始される事業年度から対象となるため、該当する法人は令和5年3月以降、順次適用初年度の決算申告を迎えます。
今回は決算を前に賃上げ促進税制の概要を確認し、適用を受けるにあたって留意すべき点や、対象範囲を誤らないための用語の定義を解説していきます。
賃上げ促進税制の概要
賃上げ促進税制は上述した通り、令和4年4月1日以降に開始する事業年度より適用できる制度です。令和4年3月31日以前の所得拡大促進税制が前身であり、これに要件の簡素化や控除率の拡大といった見直しが行われた形になります。
賃上げ促進税制には大企業向けと中小企業向けがありますが、ここでは中小企業向けについて取り上げていきます。
制度の概要
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。日本の賃金水準が長らく横ばいである現状を受けて、法人税の優遇により積極的な賃上げを促進する狙いがあります。
適用の要件 通常要件と上乗せ
下記のような要件を満たすことで、税額控除を受けることができます。
①通常要件
雇用者給与等支給額が前年度と比較して1.5%以上増加していた場合、その増加額の15%を法人税額から控除できます。
②上乗せ要件1
雇用者給与等支給額が前年度と比較して2.5%以上増加していた場合、税額控除率が15%上乗せされます。
③上乗せ要件2
教育訓練費の額が前年度と比較して10%以上増加していた場合、税額控除率が10%上乗せされます。
全ての要件を満たすことで最大で給与等の増加額の40%を税額控除できます。但し、税額控除できる金額の上限は元の法人税額の20%までである点には注意が必要です。通常、従業員の昇給を行えば社会保険料等の付随する経費も増加し、企業にとっては急激なコスト増となる懸念がありますが、税額控除により負担が軽減されるメリットは大きいと言えます。
必要書類
賃上げ促進税制の適用を受けるにあたり、事前に申請や届出は必要ありません。
従って事業年度を終えてからでも、昇給の実績を集計して適用の可否を判断することができます。
申告時には税額控除の対象となる金額が記載された書類を添付する必要がありますので、雇用者給与等支給額の前年からの増加額を計算した明細書を作成しておきましょう。また、上乗せ要件である教育訓練費の増加の適用がある場合には、教育訓練費の増加額の計算明細も作成します。こちらについて添付は不要ですが、求められた際にはすぐに開示・説明ができるように社内に保存する必要があります。
所得拡大促進税制との違い
基本要件について賃上げ促進税制は所得拡大促進税制の要件を引き継いでおり、雇用者給与等支給額が前年度と比較して1.5%以上増加している場合に、その増加額の15%を税額控除にすることにつき変更はありません。
一方で所得拡大促進税制の上乗せ要件については、雇用者給与等支給額が前年度と比較して2.5%以上増加し、かつ、教育訓練費の額が前年度と比較して10%以上増加している、又は適用年度終了日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受け、当該計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされている場合に、税額控除率が10%上乗せされるというものでした。
税額控除率が最大でも25%であり、上乗せ要件も現行のように段階的ではないため、適用のハードルが高い点もありました。
賃上げ促進税制では最大控除率が引き上げられ、上乗せ要件が給与額の増加率と、教育訓練費の増加で独立しているため、柔軟な適用が可能になり使い勝手は向上しています(経営力向上計画の要件は廃止)。
必要書類についても教育訓練費の増加額の計算明細の申告書への添付が必要だったものが、会社での保存に緩和されています。
賃上げ促進税制の適用にあたっての留意点
制度の概要は比較的明瞭であるものの、適用するにあたって実務上は留意しておくポイントがあります。特に対象となる給与や従業員の範囲について、具体的にどこまでを計算に含めるのか、判断に迷うケースが出てきます。この制度では多くの用語が出てきますが、特に計算に関係してくる重要なものをピックアップして解説していきます。
用語および範囲の定義
①対象となる法人の範囲
賃上げ促進は「中小企業者等」が前年度より給与等を増加させた場合に適用されます。
・中小企業等
青色申告書を提出している者で、資本金又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主、協同組合等を指します。
尚、法人では次のような場合は適用の対象外となります。
・前3事業年度の所得金額の平均が15億円を超える法人
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
※大規模法人とは資本金又は出資金の額が1億円超の法人、資本又は出資を有しない常時使用する従業員数が1,000人超の法人、又は、資本金又は出資金の額が5億円以上の大法人から完全支配を受けている法人をいいます。
②対象となる従業員の範囲
賃上げ促進税制は、「国内雇用者」に対して行われた賃上げ、教育訓練が対象となります。
・国内雇用者
法人の使用人で、国内にある事業所で作成された賃金台帳に記載されている従業員を指します。賃金台帳に記載があれば正社員に限らず、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。一方で法人の役員やその親族は対象にはなりません。これは一族経営を例に考えるとわかりやすいですが、経営者一族やその家族に対して賃上げを行っても、その増加部分の税額控除は認めないという事です。あくまで、純粋に従業員の昇給や教育訓練が対象になるという前提があります。
③対象となる給与の範囲
賃上げ促進税制では「雇用者給与等支給額」を前年と比較して増加額を計算します。
・雇用者給与等支給額
給料、賃金、賞与、手当が対象になります。その事業年度分の給与として算定されていれば、未払であっても含め、反対に支払っていても来年度分を前払したものであれば含めません。また、退職金は対象になりません。多額の退職金を支払って人件費を前年より増加させても税額控除は受けられないということです。
もう一つ留意する点として、給与の負担軽減を目的に交付を受けた助成金、補助金(業務改善助成金やキャリアアップ助成金等)がある場合には、この金額は雇用者給与支給額から控除する必要があります。自社の利益からではなく、補填を受けて支給している給与は除外するという考え方です。但し、コロナ感染症による事業縮小時に雇用維持のために給付を受けた助成金など、雇用安定助成金に該当するものは控除する必要がありません。少々ややこしいですが、給与関連の助成金の受給があった場合には書類をよく確認するようにしましょう。
④上乗せ要件の対象となる教育訓練費の範囲
・教育訓練費
外部講師を招聘した場合の謝礼や移動にかかる交通費、従業員の外部研修への受講料、研修施設の利用料やeラーニングの使用料、研修の委託費など多様な教育形態が対象となっています。対象外となる費用としては役員が対象の教育訓練費、福利厚生目的の強い費用、法人が所有する施設の取得・維持費用があります。
ちなみに、会社保存書類である教育訓練費の明細書には、教育訓練を行った年月日、場所、内容、受講者、費用の支払証明書類の写しが記載されている必要があります。
その他留意事項
制度の適用誤りを防いだり、会社にとって適正な活用をするには賃上げ促進税制の趣旨を理解することが肝要です。この制度の優遇措置は税額控除であることから、赤字企業は想定されていません。適正な利益を出している企業の適切な分配を促しているという大前提があります。
昇給は一度行えば以後は経常的に必要となる費用であり、安易に削減することはできません。また教育訓練は中長期的な視野で従業員のスキルアップやキャリア形成を後押しするものです。仮に税額控除欲しさに無計画に取り組んだとしても、後のコスト増が経営を圧迫したり、そもそも出費自体が無駄になってしまう点には注意しましょう。
まとめ
賃上げ促進税制によって従業員側も給料や賞与の増加に繋がるので、モチベーションやパフォーマンス向上が期待できます。教育訓練の充実により、社員のスキルアップやキャリア形成は勿論のこと、教育体制の整った企業は採用の面でも有利になります。
人材不足が懸念されるこれからの時代はこのような取組の重要度が増してくると考えられます。
反面、無計画な昇給には急激なコスト増や社員間の不和を生じさせるリスクもあります。会社として利益計画を立て、業績に応じた公正な評価制度の整備は必須です。収支のバランスを取りながら利益の向上と昇給を両輪で行う事でこの制度を活用する意義はより大きくなるのではないでしょうか。